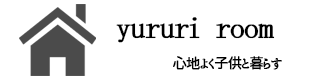ゆるり
ゆるりこんにちは。育児奮闘中のゆるりです。
非認知能力って最近よく聞きませんか?
とっても気になるので調べてみました!
子どもの成長って、テストの点数だけでは測れないものがたくさんありますよね。最近、「子供の非認知能力」という言葉が注目されるようになり自己肯定感や共感力、やり抜く力といった“見えないけれど大切な力”に目を向ける方が増えていますよね。
子どもの将来の幸せに関わる“非認知能力”がいま注目されています。本記事では、非認知能力の定義から伸ばし方、遊びや習い事の実例までを、文部科学省の資料も交えてわかりやすく紹介します
- 子どもの心の力や成長が気になるママ・パパ
- おうち遊びや関わり方で子どもの力を伸ばしたい方
- テストの点だけじゃない「生きる力」に興味がある方
非認知能力とは?いま注目される理由

非認知能力とは?文部科学省も注目する“見えない力”
非認知能力とは、テストの点数やIQなどの「数値では測れない力」のこと。人間関係、感情のコントロール、意欲や自己肯定感など、人生を豊かに生き抜くための土台となる力だとされています
自己肯定感:自分に自信を持ち、「自分は大丈夫」と思える力
やり抜く力(グリット):困難に直面してもあきらめずに努力を続ける力
共感力:他人の気持ちを理解し、思いやることができる力
感情コントロール力:怒りや悲しみなど、自分の感情を上手にコントロールする力
協調性:他の人と仲良く、協力して行動できる力
好奇心・探究心:新しいことに興味を持ち、自ら学ぼうとする姿勢
自己管理能力:自分の行動や時間、目標を管理する力
創造性:自由な発想で物事を考える力
レジリエンス(回復力):失敗やストレスから立ち直る力
子どもの将来の幸せや成功に直結すると言われており、学力以上に大切だとする研究結果もあります
なぜ非認知能力が注目されているのか?
テクノロジーの進化やグローバルなつながりの広がりによって、私たちの社会はこれまでにないスピードで変化しています。かつては学歴やテストの点数といった「見える力」が重視されてきましたが、今ではそれだけでは通用しない時代になりつつあります。
そんな中で脚光を浴びているのが、「非認知能力」と呼ばれるスキルです。これは、数値では測りにくいものの、人間関係を築いたり、自分を律したり、感情を表現したりする力のこと。こうした力は、変化の激しい社会をしなやかに生きるための土台となるものです。
文部科学省も、幼児期に育んでほしい力として「自立心」「協同性」「感性や表現力」などを挙げており、これらはいずれも非認知能力に該当します。知識やスキルだけでなく、人としての総合的な力が問われる今、非認知能力の重要性はますます高まっています。
※参考:文部科学省 教育課程部会 幼児教育部会(第2回)配付資料
 ゆるり
ゆるり昔の詰め込み式の勉強のままでは時代に取り残されそうなのは、分かる!
非認知能力の3つの柱とは?
非認知能力は、主に以下の3つの柱に分類されます
文部科学省によると、主に「意欲・意志・情動・社会性」に関わる能力で、次のようなものです。
①友達と同じ目標に向けて協力し合う
②自分の目標に向かって粘り強く取り組む
③そのためにやり方を調整し工夫する
特に幼児期(満4歳から5歳)に顕著な発達が見られ、学童期・思春期の発達を 経て、大人に近づく。
非認知能力が高い子の特徴とは?
非認知能力が高い子どもには、以下のような共通点があります:
- 新しいことにワクワクして取り組む
- 負けても立ち直る力がある(レジリエンスが高い)
- 他人の気持ちを考えて行動できる
- 自分の気持ちを言葉で伝えられる
- 集中力や粘り強さがある
非認知能力を伸ばすには?家庭でできる方法

子どもの非認知能力を伸ばすには、**「関わり方」+「遊び」+「環境づくり」**の3つが大切です。
✅ 子どもの非認知能力チェックリスト(簡易版)
- ✔ 自分の気持ちを話せる
- ✔ 負けても泣かずに切り替えられる
- ✔ 順番やルールを守れる
- ✔ 初めての場所・人にも興味を持つ
- ✔ コツコツ何かをやり遂げた経験がある
このような項目が多く当てはまる子は、非認知能力が高い傾向があります。
非認知能力を高めるおすすめの遊び5選

1. ごっこ遊び(お店屋さん・お医者さんなど)
- 育つ能力:想像力、共感力、社会性
- ポイント:ルールを決めたり、他人の役を演じることで、社会性が育ちます。
2. 積み木やブロック遊び
- 育つ能力:集中力、創造性、問題解決力
- ポイント:自由な発想で形を作ることで、成功体験と自信が身につきます。
3. 外遊び・自然体験(虫とり、山遊びなど)
- 育つ能力:好奇心、忍耐力、協調性
- ポイント:自然とふれあう中で、探求心や身体的なチャレンジ精神が育ちます。
4. 絵本の読み聞かせ
- 育つ能力:感情理解力、語彙力、集中力
- ポイント:物語に共感する力が育ち、心の幅が広がります。
5. ボードゲーム・カードゲーム
- 育つ能力:ルール理解、感情コントロール、勝ち負けの受け入れ
- ポイント:順番を待ったり、負けを経験することで、社会性や我慢強さが身につきます
スポーツは非認知能力を高める?

東京成徳大学の夏原隆之助教授による研究結果などから、スポーツは非認知能力を育むことが明らかになっています
スポーツ経験と非認知能力の関係
スポーツ経験のある子どもは、
スポーツ未経験の子どもに比べて、以下のような非認知能力が高い傾向があります:
- 自制心(感情や欲求をコントロールする力)
- 忍耐力(努力を続ける力)
- レジリエンス(困難から立ち直る力)
- 自己効力感(自分にはできるという感覚)
- 動機づけ(自ら目標を設定して行動する力)
- メタ認知(自分の思考や行動を客観的に理解する力)
これらは学力とは別の、将来の人間的成長や成功に深く関係する力として注目されています。
1. 目標を立てることの大切さ
目標を達成するためには、目標の立て方が重要です。曖昧な目標では達成が難しく、次の5つのポイントを押さえることが大切です:
① 具体性、② 測定可能性、③ 達成可能性、④ 価値観との一致、⑤ 時間の制約。
これらを踏まえて目標を立てることで、行動につながり、成長に結びつきます。
2. 主体的な取り組みが成長のカギ
練習や勉強は、自ら進んで行うことで効果が高まります。トレーニング科学でも「意識性の原則」として、自発的な取り組みの重要性が強調されています。
3. スポーツは知力や人間力の向上に役立つ
スポーツをすることで、記憶力や思考力が高まり、学力の向上にもつながると研究で示されています。心肺機能が高い人ほど成績が良い傾向もあります。
4. スポーツが育む“非認知能力”
スポーツを通して得られる粘り強さや協調性、自己コントロール力などの「非認知能力」は、生きる力となり、将来的な成功や人間的成長にも深く関係しています。
結論
スポーツは、健康だけでなく学力や人間力を高め、より良い人生をつくるためにも重要です。学習と同様に、主体性と明確な目標を持って取り組むことが成功のカギです。
非認知能力を伸ばすには?家庭でできる方法
子どもの非認知能力を伸ばすには、**「関わり方」+「遊び」+「環境づくり」**の3つが大切です。
非認知能力を育てる家庭での関わり方

遊びに加えて、親の関わり方も重要です。
- 「できたね!」と小さな成功体験を褒めてあげる
- 子どもが失敗しても、責めずに励ます
- 一緒に遊びながら、対話を大切にする
- 子どもの「なぜ?」を大切にして探求を促す
これらの姿勢が、子どもの非認知能力を自然と伸ばします。
非認知能力を高める習い事は?
習い事も、非認知能力の育成に効果があります。特におすすめなのは:
- 体操・運動系:挑戦・継続・失敗からの学びがある
- 音楽・アート系:表現力や創造性が伸びる
- 演劇・表現活動:自己肯定感や共感力が育つ
- 茶道・武道:礼儀・集中力・忍耐力が鍛えられる
ポイントは「結果よりも過程を大切にする習い事」を選ぶことです。
非認知能力の言い換え・関連用語
非認知能力は以下のような言葉で表現されることもあります:
- ソフトスキル
- 社会情動的スキル(SEL)
- EQ(感情知能)
- 生きる力
- 人間力
どれも、“人としての基礎力”として、将来にわたって重要な能力です。

非認知能力に関するまとめポイント
- 非認知能力とは、「見えないけれど人生に大切な力」
→ テストの点では測れない、自己肯定感・共感力・やり抜く力などを指す。 - 非認知能力は“生きる力”や“人間力”の土台
→ 将来の幸福度・成功・人間関係などに大きく影響する。 - 文部科学省も幼児期からの育成を推奨
→ 「自立心」「協同性」「感性・表現力」などがその一例。 - 非認知能力は主に3つの柱で育まれる
① 協力する力 ② 粘り強く取り組む力 ③ やり方を工夫する力 - スポーツは非認知能力の成長に効果的
→ 自制心、レジリエンス、自己効力感などが自然と育つ。 - 非認知能力が高い子には共通する特徴がある
→ 新しいことに意欲的、共感力がある、失敗から立ち直れる など。 - 家庭での「関わり方+遊び+環境」が鍵
→ 褒める・対話する・探求を応援するなどの親の姿勢が重要。 - 日常の遊びが非認知能力を育てる機会に
→ ごっこ遊び、外遊び、絵本、ボードゲームなどが有効。 - おすすめの習い事は「過程を大切にする」もの
→ 体操、アート、演劇、武道などが子どもの心を育てる。 - これからの時代は、学力だけでは不十分
→ 変化の激しい社会を生き抜くには、非認知能力の育成が不可欠。
非認知能力は、テストの点数では測れない“生きる力”です。そしてその力は、遊びの中でこそ自然に、楽しく育まれます。非認知能力は、数値化できないけれど、人生の幸福度や成功に大きく影響する力。
遊び・習い事・親の関わりを通して、家庭でも今すぐ伸ばしていくことが可能です。
「遊びは学び」──この考え方が、子どもの未来をより豊かにしてくれます。
 ゆるり
ゆるり「遊びながら育てる」を合言葉に、子どもが持つ力を最大限に引き出していきたいですね。
 ゆるり
ゆるりブログにお越し下さってありがとうございます。
こんにちは。3児の育児奮闘中のゆるりです。プロフィールはこちらです♡
子供と一緒にやりたいことリストを作りゆるっと実行中です。
最近、ママのやりたい事リストも加えてゆるっとブログを更新してます。
どうぞよろしくお願いします。